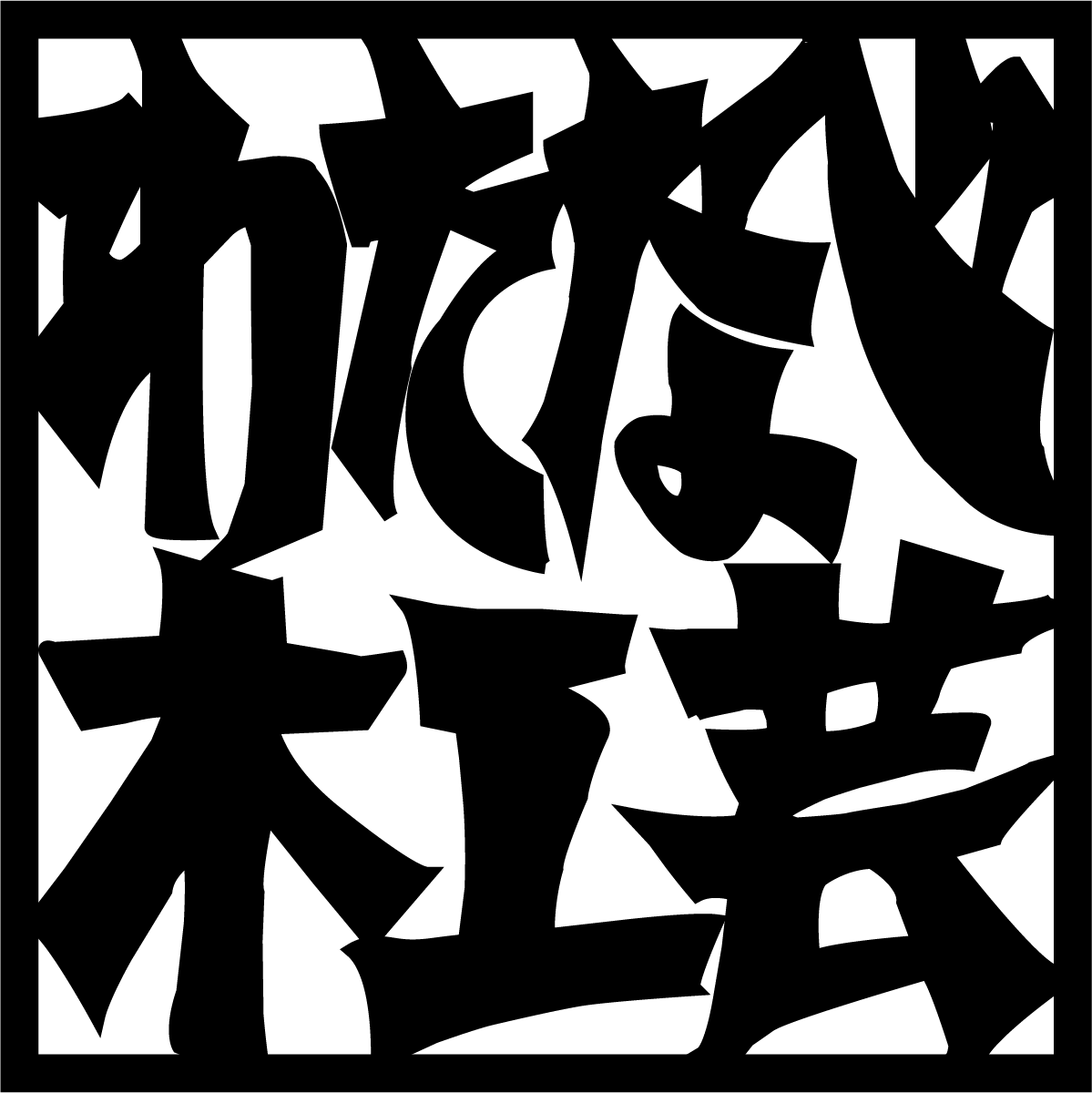2025/06/21 11:49

こんにちは。
わたなべ木工芸の渡辺です。
今回は、よく聞かれるこの質問についてお話ししたいと思います。
「どうして“木のペン”を作っているんですか?」
この問いには、僕自身の仕事の歩みや、伝統工芸との関わり、そして未来への想いが詰まっています。
少し長くなりますが、読んでいただけたら嬉しいです。
伝統工芸の家に生まれて
僕は富山県南砺市(なんとし)で、家族とともに木工の工房を営んでいます。
現在は、木のシャーペンやボールペン、いわゆる木軸ペンを主に製作しています。
もともとこの工房は、漆器の木地を専門に作ってきた場所でした。
庄川挽物木地(しょうがわひきものきじ)という伝統工芸で、
お椀やお盆の木の土台を作る職人の仕事です。
僕で三代目。
わたなべ木工芸はこの技術を75年以上にわたって受け継いできました。
しかし、今では庄川挽物木地の産地の全体でも職人の多くが70代。
しかし、今では庄川挽物木地の産地の全体でも職人の多くが70代。
僕は18年前にこの道に入りましたが、それ以来ずっと最年少のままです。
このままでは伝統が途絶えてしまう、そんな危機感を日々感じています。
ペン作りのきっかけは「端材」
ペン作りのきっかけは「端材」

そんな中で木のペンを作り始めたきっかけは、工房に山のように積まれていた端材でした。
欅(けやき)、黒柿(くろがき)、紫檀(したん)など、どれも良質な木ばかり。
でも器にするには小さすぎて、長年手を付けられずにいたんです。
この木たちを、なんとか活かせないだろうかと考えていたときに出会ったのが、
ペンターニングという木工旋盤を使ったペンづくりでした。
それが、今の仕事の原点です。
当初はあくまで漆器の合間に少しずつ作っていたのですが、
そこから少しずつ方向が変わっていくことになります。
百貨店からネット販売へ、そして転機へ
その頃は、全国の百貨店を回って漆器を販売していました。
両親と三人で、1週間ごとに各地を巡って、がむしゃらに働いていました。
ですが、そんな生活が一変したのがコロナの影響でした。
百貨店への出店はすべて中止。
そこからはネット販売へと切り替え、写真を撮ったり、文章を書いたり、動画を作ったり
手探りで、自分たちのものづくりを発信するようになりました。
最近漆器を作ってない理由
その後、2024年に起きた能登半島地震。
輪島、漆器の聖地のような場所が大きな被害を受けた様子を見て、
漆器を販売することへの気持ちが重くなってしまいました。
今、自分が漆器を売るべきではないのではと感じたこともあり、
漆器のことを発信する事からは離れることを決めました。
そんな中で、木軸ペンに関する動画が少しずつ反響を得て、
もしかしたら、これは次の道かもしれないと思い切って方向転換しました。
SNSを通じて届く声が励みに
ありがたいことに、今ではSNSを通じて
「買いました!」「届きました!」という声をいただけるようになりました。
以前はご年配の方を主な対象にしていたものづくりから、
今は若い世代の方にも届くようになったことが、本当に嬉しいです。
一時はどうなるかと不安でいっぱいだったので、今こうして続けていられることに感謝の気持ちでいっぱいです。
僕が木のペンを作る理由(3つ)
僕が木のペンを作っている理由は、3つあります。
1つめは、端材を活かしたかったから。
捨てるにはもったいない、でも器には使えない。そんな木を別の形で生かしたかった。
2つめは、日本の良い木を日常に使ってほしかったから。
欅や黒柿、桑など、日本には素晴らしい木がたくさんある。
それをもっと身近に感じてもらいたい。
3つめは、伝統工芸の技術をつなぎたかったから。
後継者がいない中で、長く続いてきた木地師の技術をなんとかつなぎたい。
それは簡単なことではないと思います。
儲かる仕事ではないし、若い人に苦労を背負わせたいとも思っていない。
だからまずは知ってもらうことが大切だと考えています。
「木地師がつくる木軸ペン」という言葉に込めた想い
わたなべ木工芸の作るペンには「木地師がつくる木軸ペン」という言葉がついています。
みなさんに木地師という言葉を知ってもらう事、微力ですが、それが今の僕にできる事なのかなっと
思ってやってます。
YouTubeチャンネルを始めたのも、
伝統工芸の技術や工房の風景を残したいと思ったのがきっかけでした。
今はペンの事を発信する事に追われてなかなか伝統工芸や技術的な事の撮影ができていませんが、
いつかまた、そういった動画も発信していけたらいいなと思っています。
応援してくださる皆さまへ
今は、ペン売上が動画制作の資金になっています。
見てくださった方が買ってくださることで、次の動画が作れる
そんな循環が少しずつできてきています。
木のぬくもりを感じられるモノを、これからもひとつひとつ丁寧に作っていきます。
そして「職人系YouTuber」としての発信も引き続き頑張っていきたいと思っています。
よかったら、YouTubeのチャンネルのほうもチェックしていただけると嬉しいです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。