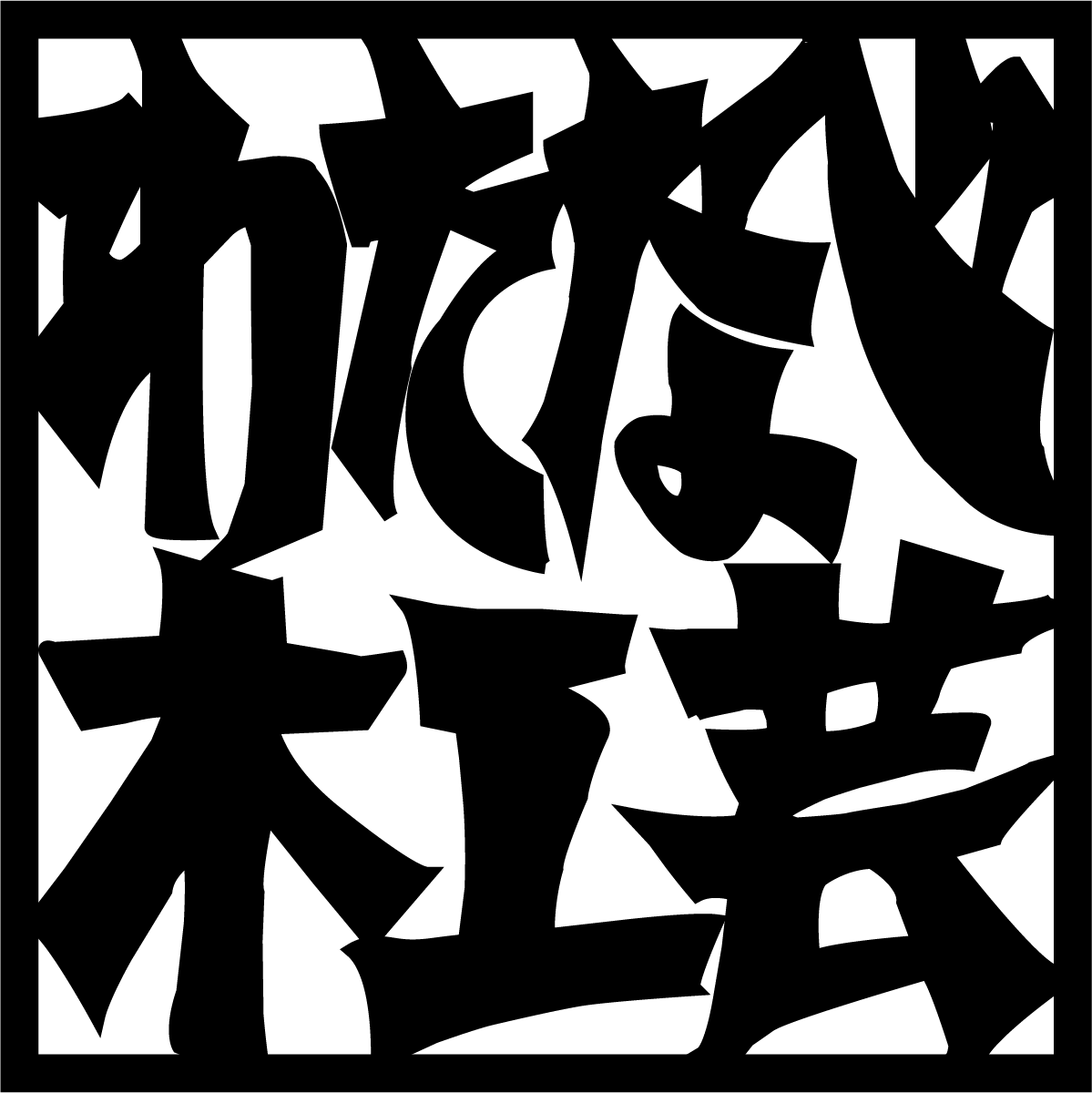2025/06/27 17:31

こんにちは、わたなべ木工芸の渡辺です。
今回は、わたなべ木工芸で最も多く使ってきた木材「欅(けやき)」についてご紹介します。
欅は日本の伝統工芸にとって、とても身近でありながら特別な存在。僕自身、この木に育ててもらったような感覚があります。木軸ペンを作るうえでも、欅はとても大切な材料です。
この記事では、欅という木の魅力や、僕がどんなこだわりを持って欅を選んでいるのかをお話ししていきます。
欅(けやき)ってどんな木?
欅は、日本でとても身近でありながら、格式のある木でもあります。
日本の広葉樹の中でも代表的な存在で、古くから生活の中に使われてきた木材のひとつです。
そのため、日本人にとってはとても馴染みのある木材であり、親しみを持って受け入れられてきました。
特徴としてまず挙げられるのは、その美しい木目。
欅の木目は、早く成長する春から夏にかけての「早材」と、ゆっくり成長する秋から冬にかけての「晩材」が交互に重なって年輪となり、はっきりとした縞模様を作り出します。
これにより、欅ならではの縞模様のような美しい木目が現れます。僕の工房では、こうした木目がはっきりと模様のように浮かび上がる部分を厳選して使っています。
さらに、希少ですが「杢(もく)」と呼ばれる特別な模様が現れることもあり、
これは自然が生み出すアートのような存在です。
欅は見た目の美しさに加えて、硬さと粘り強さを併せ持つ非常に優れた素材でもあります。
そのため、神社仏閣の柱や梁として使われたり、昔のタンスや座卓、漆器の木地など、さまざまな用途で重宝されてきました。
僕が育ったこの工房でも、欅は本当にたくさん使われてきました。
工房では、欅を木工ろくろで回しながら削って、お盆やお皿を作っていました。
仕上がりの木目を読みながら刃物をあてていくと、欅の美しい木目が浮かび上がってくるんです。
仕上がった面はしっとりと手になじんで、つややかで、触れるたびに嬉しくなる。
そういう瞬間に、欅という木の魅力をいつも感じていました。
なぜ欅を一番多く使ってきたのか?
わたなべ木工芸では、昔から欅を使ってお盆やお皿を作ってきました。
欅の木目を活かした器は見た目にも美しく、しっかりとした強度もあり、使い心地も良いことからとても人気がありました。
長く使える道具として、多くの家庭に喜ばれてきました。
そんな背景もあり、欅は僕たちの工房にとって最も多く使われてきた木材になりました。
その理由は、やはり“需要の多さ”にあります。
昔から、日本中で欅はとても人気のある木でした。
木目が綺麗で、硬くて丈夫。
見た目も使い心地も良い、まさに優等生の木なんです。
仏壇や建具、家具や器、さまざまな工芸品に使われてきたのも、そういう理由があると思います。
日本人にとって欅という木は、やっぱり“特別な存在”だったんじゃないかと感じています。
ペンに使う欅は“なんでもいい”わけじゃない
ただ、木軸ペンに使う欅は、なんでもいいわけではありません。
僕の工房では、木目が細かくて美しいものを厳選しています。
さらに、特別な模様──「杢(もく)」と呼ばれる不規則な波模様が出ているものや、「上杢目(じょうもくめ)」と呼ばれる、
老木の根に近い部分などに現れる貴重な木目を中心に使っています。
“杢”というのは、木の中に現れる特別な模様のこと。
人工的には作れない、自然が生んだアートのような模様です。
実は、そういった欅は、うちにあるストックの中でも5%もありません。
それくらい希少で、昔の職人たちも大切にしてきた部位です。
今は、そうした“上等な欅”から優先的に使っていて、
いずれ在庫が少なくなれば、普通の木目の欅に切り替わっていく予定です。
いずれはこのレベルの欅が出せなくなる可能性もあるので、今は特におすすめできるタイミングです。

おわりに
欅は、わたなべ木工芸にとっても、日本の工芸にとっても、特別な木です。
その中でも、木目や杢にこだわって選んだ欅だけを使って、一本一本、丁寧に木軸ペンを作っています。
工房としても、長年欅と向き合ってきた歴史があるからこそ、この素材の良さを活かす技術があります。
今出している欅は、自分でも「よくこの価格で出せてるな」と思うほど良いものばかりです。
木軸ペンに興味がある方には、ぜひ“今のうちに”手に取ってみていただけたら嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
では、またー!
では、またー!
よく読まれています