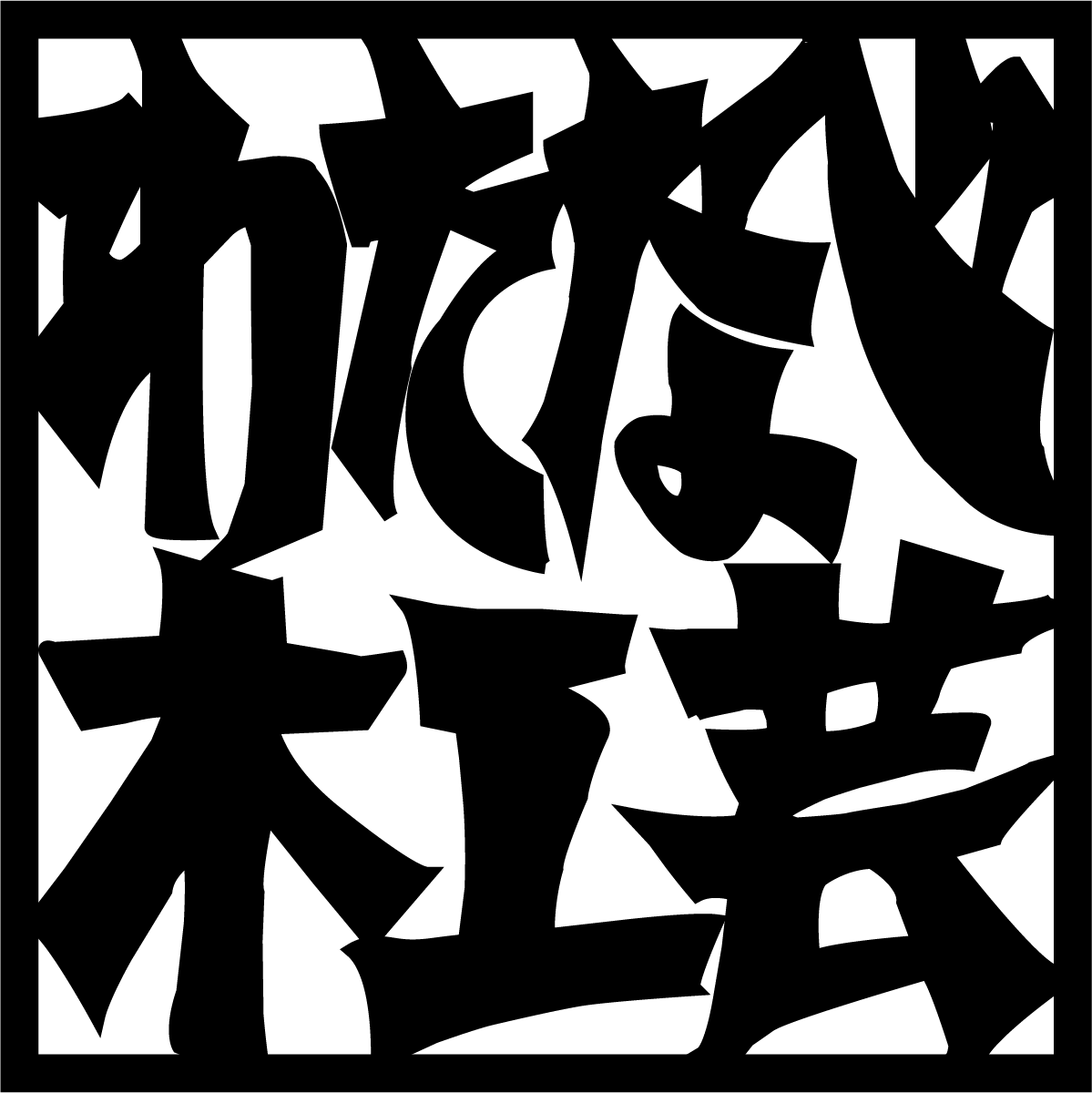2025/10/20 16:44

「桑(くわ)」という木を知っていますか?
名前は聞いたことがあっても、実際に木材として触れたことがある方は少ないかもしれません。
でも実はこの桑、昔から日本の暮らしと深く関わってきた木なんです。
明るくやさしい色合い、そして使い込むほどに深みを増していく色とツヤ。
その変化の美しさから、日本の伝統工芸品の中でもとても重宝されてきた木です。
木のペンの素材としても、木目や経年変化を楽しみたい方にとって、桑はまさにぴったりの素材です。
日本の文化に馴染みのある木だからこそ、知るほどに愛着が増していく。
この記事では、そんな桑の魅力をわかりやすくご紹介します。
【産地】
桑の木は、日本全国に自生しており、特に東北から中部地方にかけて多く見られます。
昔は「養蚕(ようさん)」といって、絹(シルク)を作るために蚕(かいこ)を育てる仕事が日本各地で盛んに行われていました。
蚕は桑の葉を食べて育つため、農家の庭や畑のそばに桑の木がたくさん植えられていたんです。
つまり桑は、日本人の暮らしとともに育ってきた木。
春になると柔らかな新芽を出し、夏には濃い緑の葉を茂らせるその姿は、どこか懐かしく心を和ませてくれます。
今では養蚕業の衰退とともにその風景も少なくなりましたが、
桑の木は今もなお、「日本の手仕事文化を支えてきた木」として、静かにその存在を残しています。
【歴史・文化】
桑の木は、古くから日本の“ものづくり文化”を支えてきた存在です。
蚕(かいこ)を育てるための木として、養蚕業の中心にありました。
蚕が食べるのは桑の葉だけ。
その葉から生まれる繭(まゆ)から絹糸が作られ、やがて着物や帯、工芸品へと形を変えていきます。
つまり桑は、「絹の文化」を支えた木。
日本人の衣・文化・暮らしのすべてに深く関わってきたのです。
また、桑は“繁栄”や“長寿”の象徴としても大切にされてきました。
そのため、昔の人々は家の敷地に桑の木を植え、幸せを願ったとも言われています。
そんな背景を知ると、木軸ペンとしての桑にも、どこか“日本らしいあたたかさ”を感じられますよね。
【特徴・性質】
桑の木は、硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどよい弾力を持った木です。
木工職人の間では「削っていて気持ちいい木」として知られており、加工性が高く、細部まできれいに仕上がります。
木の繊維がしなやかで、しっかりとした強度もあるため、長く使う道具に向いています。
また、油分を少し含んでいるため、表面はなめらかで手触りがよく、使い込むほどに艶が深まっていくのが特徴です。
時間とともに少しずつ色が変わり、まるで持ち主と一緒に歳を重ねていくような温かさがあります。
「使いながら育てていく」そんな楽しみ方ができる木材です。
【木目】
桑の木目は、やさしく穏やかな印象です。
はっきりした木目の中に、ほんのりと揺らぎがあり、見る角度によって光の反射が変わります。
(よく見るとキラキラして見えます)
(よく見るとキラキラして見えます)
一本のペンの中に、静かな動きを感じるような表情が生まれるのが魅力です。
ときには「縮み杢(ちぢみもく)」や「玉杢(たまもく)」と呼ばれる美しい杢(もく)が現れることもあります。
その部分は特に人気が高く、木軸ペンとしても唯一無二の存在感を放ちます。
派手ではないけれど、見るたびにほっとするようなやさしさ。
それが、桑の木目が持つ魅力です。
【色】
桑の木の一番の魅力は、そのやさしく温かみのある色合いです。
削りたての木は、明るい黄褐色や淡い黄金色をしており、まるで光を含んだような柔らかさがあります。
一方で、濃い茶色に近い深い色味のものも多く、同じ桑でも一本ごとにまったく違った表情を見せてくれます。
そして、ここからが桑の楽しみ。
使い込むうちに少しずつ色が変化し、やがて落ち着いた飴色へと深まっていきます。
木軸ペンに仕立てると、手の油分や光の当たり方で艶が増し、まるで時間をまとっていくよう。
新品の明るさも、年月を経たあとの渋みも、どちらも美しい。
その「色の経年変化」こそが、桑の木の魅力です。
【匂い】
桑の木は、強い香りはありませんが、削った直後はほんのりと甘い香りがします。
乾燥するとほとんど無臭になり、自然素材らしいやさしい香りがわずかに残る程度です。
控えめで落ち着いた、心地よい香りです。
【硬さ】
桑の木は、中くらいの硬さで、ほどよいしなやかさがあります。
削ったときの抵抗感がちょうどよく、木軸ペンとしても扱いやすい素材です。
傷も付きにくいので、毎日使うペンとしても安心してお使いいただける硬さがあります。
【用途】
桑の木は、古くから日本の工芸で重宝されてきた木です。
あたたかみのある色合いと、落ち着いた木目が美しく、
家具や仏具、楽器、彫刻など、さまざまなものに使われてきました。
わたなべ木工芸でも、かつては無塗装のお盆の最高級品として桑を使っていました。
仕上げをせず、木そのものの質感と色の変化を楽しむ——そんなお盆は、
年月とともに飴色へと深まり、長く使うほどに味わいを増していくとても人気の品でした。
その性質は、木軸ペンにも通じています。
使うほどに艶を帯び、少しずつ自分だけの色へと育っていく。
まさに“時を重ねて美しくなる木”なのです。
【希少性】
桑の木は、昔から日本各地で親しまれてきましたが、
実は大きく育たない木なんです。
ゆっくりと成長するため、太い幹の材を得ることが難しく、
昔から「高級材」として扱われてきました。
現在では良質な桑材が手に入りにくくなり、
特に杢(もく)が入ったものは非常に貴重です。
【経年変化】
桑の木は、時間とともにゆっくりと色が深まり、艶が増していく木です。
使い始めは明るい黄褐色や黄金色ですが、少しずつ飴色へと変化します。
この変化は、使う人の手の温度や油分、日々の光の当たり方によって表情が変わり、
まるで持ち主と一緒に歳を重ねていくような感覚を楽しめます。
新品の時よりも、数年後がいちばん美しい。
それが、桑という木のいちばんの魅力です。
【まとめ】
桑の木は、古くから日本の暮らしとともに歩んできた木です。
大きく育たない分、ひとつひとつの材に力強さと上品さがあり、
色の変化や木目の美しさをゆっくりと味わうことができます。
使うほどに深みを増し、艶が育ち、手に馴染んでいく。
まるで時間そのものを閉じ込めたような木——それが桑です。
当工房で制作している桑の木軸ペンも、
明るい中にも落ち着きがあり、経年変化の美しさをたっぷりと楽しめる一本に仕上がっています。
「育てるように使うペン」をお探しの方に、ぜひ手に取っていただきたい素材です。
わたなべ木工芸では、国産の木を中心に一本ずつ丁寧に仕上げた木軸ペンをご用意しています。
気になる方は、ぜひこちらからご覧ください。