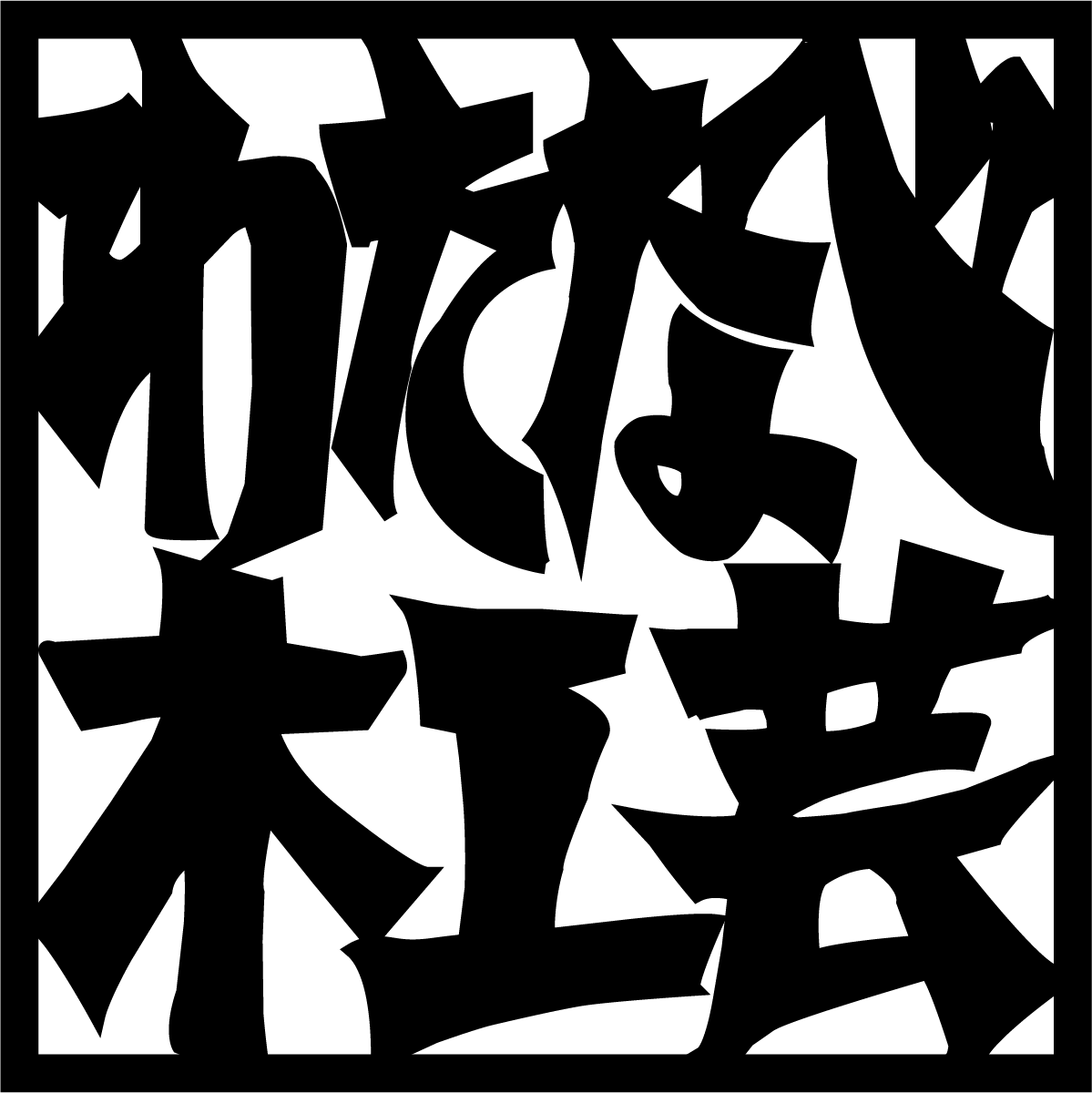2025/11/25 15:56

黄檗(きはだ)は、昔から薬の材料として知られる木。
木材としては、どこか大人っぽくて、派手さはないのに心に残る存在感があります。
木軸ペンにすると、その渋さが一段と引き立って “カッコいい” 雰囲気になる木でもあります。
僕自身、このきはだで作る木軸ペンがひそかにお気に入りで、手に取った瞬間に「やっぱりいいな」と思わせてくれる材です。
こちらの記事では、そんな”きはだ”の特徴をまとめてみました。
どうぞ、ゆっくりお楽しみください。
【産地】
きはだは、北海道から本州の山あいまで、比較的涼しい地域に広く自生する木です。
川の近くや日当たりのやさしい斜面など、清らかな水と風が通る場所を好んでゆっくり育っていきます。
昔から農村や山里の暮らしと結びつきが深い木で、山仕事に出かけた人たちが薬として内皮を採ったり、染料として使ったりと、生活のすぐそばにある存在でした。
【歴史・文化】
きはだは、古くから日本人の暮らしを支えてきた“薬木(やくぼく)”として有名です。
樹皮の内側からとれる「黄柏(おうばく)」は漢方薬の材料として重宝され、
体を整える薬として今も使われています。
また、この黄柏の鮮やかな黄色は、昔は染料としても利用されていました。
晴れた日の光を思わせるような柔らかな黄金色で、紙や布、仏具などを染めるのに使われ、どこか神聖な雰囲気をまとっています。
邪気を払う色として扱われた時代もあり、儀式の場や守りの意味を込めて使われることもあったそうです。
きはだは決して派手な木ではありませんが、日本の文化の中で“静かに人を支える木”として、長い年月にわたり親しまれてきました。
【特徴・性質】
きはだは、ほどよい硬さと粘りを持つ、扱いやすい広葉樹です。
木工の現場でも「素直で、道具に逆らわない木」といわれることが多く、切削するときの刃あたりもやさしい材です。
わたなべ木工芸では、昔、急須や片口などを一つの木の塊からお削り出しで作っていたのですが、
その時に使っていた木材はこのきはだです。
けやきのようにきれいな木目がでているけど、削りやすい木として重宝していました。
木軸ペンにすると、その素直さが手触りによく表れます。
握った瞬間に“スッ”と馴染む質感があり、どこかしっとりと温かく感じる木材です
【木目】

きはだの木目は、基本的にまっすぐで素直。
奇抜さはありませんが、その落ち着いた表情が、“品よくまとまる”木でもあります。
そして、きはだの魅力として忘れてはいけないのが、ごく稀に現れる「 縮み杢(ちぢみもく)」です。
細かく波打つようなこの杢は、光が当たるとキラッと見えたり、ゆるやかに表情を変えます。
ペンになったとき、この縮み杢は「控えめなのに、つい見入ってしまう」存在感を放ちます。
素朴なのに、よく見ると奥行きがある。
そんな“渋い美しさ”を持った木目です。
【色】
きはだの色は、少しカーキがかった落ち着いた黄褐色。
派手さはありませんが、手に取ると「おっ」と感じる渋さと高級感があります。
使い続けるうちに、色はゆっくりと深まり、より濃い色へと変化していきます。
使い込むうちに手の油分が少しずつ染み込むことで、全体に自然な艶が増していきます。
使う人だけの“味”が出るのも魅力のひとつ。
時間が経つほどに、渋い風合いがよりカッコよく育っていきます。
【匂い】
きはだは、加工しているときにほんのり木の香りがしますが、
完成した木軸ペンでは ほとんど無臭 に近い木です。
香りが強く残らないぶん、日常使いの道具としてとても扱いやすく、長く使っていても気にならない、やさしい存在です。
【硬さ】
きはだは、“中くらいの硬さ”に分類される木です。
硬すぎず、柔らかすぎず、そのちょうどよさが、木軸ペンとしてとてもバランスの良い材になります。
握ったときは軽やかで、指先にふわっと馴染む感覚。
書き続けても疲れにくく、手にストレスを与えにくいのが特徴です。
使えば使うほど「ちょうどいい硬さだな」と感じたくなる、そんなやさしい材質です。
【用途】
きはだは、古くから薬木として親しまれてきたほか、
家具材、器具材、建具など、生活に寄り添う用途で幅広く使われてきました。
とくに内皮からとれる「黄柏(おうばく)」は、
漢方薬の材料や染料として重宝され、日本の暮らしを静かに支えてきた存在です。
木としてのクセが少なく扱いやすいため、器や小物などにも適しており、
素直な木目と落ち着いた色味が“そばに置きたい道具”として愛されてきました。
わたなべ木工芸では、縮み杢(ちぢみもく)が細かく入った美しい材にを木軸ペンとして
仕上げています。
渋い中にも品があり、男女問わず手に馴染む木です。
【希少性】
きはだ自体は日本の山で比較的よく見られる木ですが、
美しい縮み杢(ちぢみもく)が細かく入る材となると、ぐっと数が限られてきます。
まっすぐ素直な木ほど杢は生まれにくく、
自然の条件がたまたま重なったときにだけ現れるため、
職人の目から見ても「おっ」と思える材には、なかなか出会えません。
まさに一期一会(いちごいちえ)。
だからこそ、縮み杢のきはだに出会えた日は、
つい手に取りたくなるような、静かな嬉しさがあります。
その一期一会の出会いを、木軸ペンにしています。
【経年変化】
きはだは、時間とともにゆっくり深みが増していく木です。
使い始めはカーキがかった黄褐色ですが、使い込むほどに、少しずつ濃い色へと育っていきます。
手の油分で表面に自然な艶が生まれ、
毎日触れている人にしか分からない“小さな変化”が積み重なっていきます。
半年も使えば、「最初とは雰囲気が変わってきたな」と感じられるほど。
渋い木だからこそ、経年変化がとてもよく似合い、
気づけば“自分の色”に育っている、そんな楽しみがあります。
【まとめ】
きはだは、華やかではないけれど、静かに心を惹きつける木です。
素直な木目と渋い色合い、そしてじっくり育っていく色の変化。
「落ち着き」や「品」を大事にしたい方におすすめです。
木軸ペンにすると、軽やかな握り心地と、ふと眺めたときに感じる“大人の雰囲気”。
毎日使う道具だからこそ、この控えめで上品な存在感がちょうど良い。
当工房で制作している きはだの木軸ペン も、杢(もく)や色味をしっかり選びながら、
「長くそばにおける道具」として丁寧に作っています。
ぜひ、あなたの手でゆっくり育ててあげてくださいね。
わたなべ木工芸では、日本の伝統工芸に馴染みのある木を中心に一本ずつ丁寧に仕上げた木軸ペンをご用意しています。
気になる方は、ぜひこちらからご覧ください。