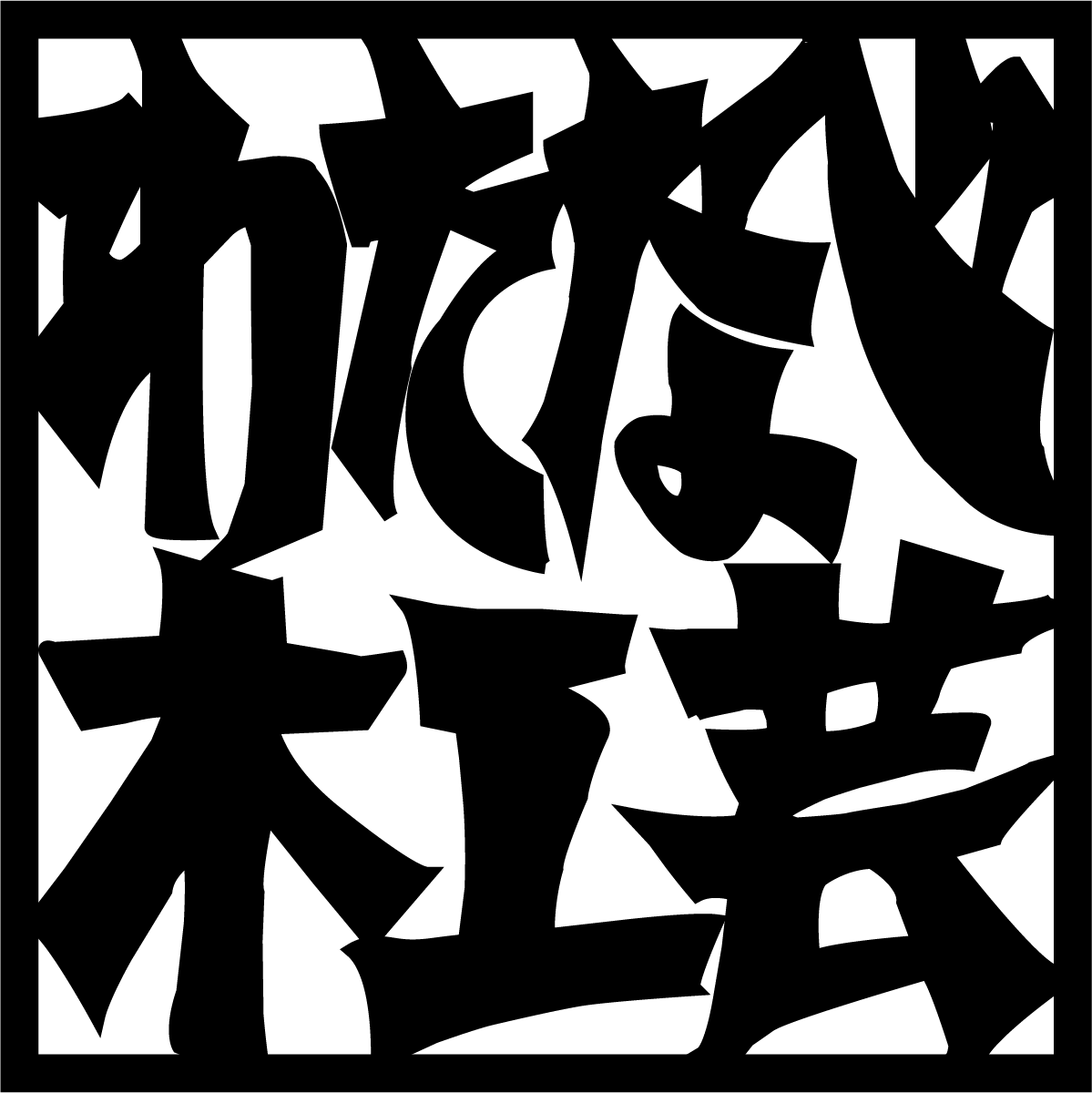2025/11/14 15:13

漆は、日本人の暮らしのすぐそばで、1000年以上使われ続けてきました。
その背景には 「日本だからこその理由」 があります。
その背景には 「日本だからこその理由」 があります。
漆は、ただ塗って乾かすだけの仕上げではありません。
湿度や温度の違いにすぐ影響を受けてしまう、思った以上にデリケートな素材です。
そんな扱いの難しい漆が日本で根づいたのは、
日本が四季があり、湿気が多く、木と暮らす文化があったから。
気候と生活の両方が、自然と漆の技を支えてきたんですね。
そして現代では、
その伝統技法をもっとも身近に味わえる存在のひとつが 木軸ペン です。
手に取るたびに、1000年以上続いてきた日本の技が、そっと日常に寄り添ってくれます。
この記事では、
「漆はなぜ日本で発展し、なぜ伝統技術と呼ばれるのか」
その理由を、分かりやすくお話ししていきたいと思います。
漆という素材は“日本の気候”だからこそ扱えた
漆塗りの技術が日本で育った大きな理由のひとつは、
「湿度で固まる」という、とても珍しい性質を持っているからです。
一般的な塗装は風通しのいい場所で乾かしますが、
漆はその逆で、湿度がないと固まりません。
湿度が足りない場所では、いつまでもベタつきが残り、仕上がらないことさえあります。
そんな漆にとって、日本の気候は理想的な環境でした。
日本は四季があり、雨も多く、年間を通して湿度が高い。
この“湿度の高さ”が、漆を硬く、美しく仕上げるためにぴったりだったのです。
そして日本の職人たちは、
漆を乾かすための特別な環境「ムロ(室)」を作り、
温度と湿度を細かく調整しながら仕上げてきました。
漆がよく乾く日に、
ゆっくりと艶が生まれていくあの感じは、
日本の気候があってこそ生まれたものでもあります。
素材の性質と、日本の気候がうまく噛み合ったことで、
漆という技術は長い時間かけて育っていきました。
日本は“木の国”。木の文化が漆技術を支えた
漆が日本で発展したもうひとつの理由は、日本人の暮らしの中心に“木”があったことです。
古くから日本の家は木で建てられ、
食器や家具、道具までもが木製でした。
僕は元々は、この漆塗りの木製の食器(漆器)の職人でした。
山に囲まれた日本では、木はどこにでもあり、
暮らしのすぐそばにある“身近な素材”だったのです。
そんな木を長く、美しく使うために選ばれてきたのが、漆。
漆を塗ることで、木が湿気や傷に強くなり、艶やかさも生まれる。
木と漆は、相性のよい組み合わせだったのです。
また、漆は木の呼吸を止めないため、
木の器も家具も、自然に馴染むように仕上がります。
長い年月をかけて使い続けられるのは、この“木と漆の調和”があるから。
器やお椀、箸、仏具、調度品──
どれも木と漆の組み合わせによって守られ、
日本の暮らしに欠かせない道具として使われてきました。
木のある暮らしが当たり前だった日本だからこそ、
漆は生活の技術として根づき、磨かれていったのです。
日本の建築文化が漆技術を育てた──神社仏閣から首里城まで
漆の技術が日本で受け継がれてきた背景には、
日本の建築文化の存在が大きく関わっています。
神社やお寺といった宗教建築は、
何十年、何百年という時間を前提につくられます。
雨も湿気も多い日本で、木の建物を長く守るためには、
強さと美しさを両立した仕上げが必要でした。
そこで選ばれてきたのが「漆」です。
漆には防水性・防腐性・抗菌性があり、
木材を湿気や虫から守りながら、深い艶を与えてくれます。
仏像や調度品が千年以上残っているのは、この漆の力が大きいのです。
そして、この漆の技術のすごさは本州だけにとどまりません。
たとえば 沖縄の首里城。
鮮やかな朱色がとても印象的ですが、
あの美しい赤は漆によって仕上げられています。
強い日差しと海風という過酷な環境にも耐えるのは、
漆が持つ耐久性の高さゆえです。
2019年の火災では、
正殿・北殿・南殿などの主要な建物が焼失してしまいましたが、
今は復元工事が進んでいて、また漆で朱色をよみがえらせる作業が続いています。
本州の神社仏閣、そして沖縄の首里城。
文化も気候も異なる土地で、同じく“漆”が使われてきたという事は、
漆が日本全体で信頼されてきた証でもあります。
さらに日本には、壊れたら捨てるのではなく、
漆を使って修復し、
また次の時代へつないでいく“直す文化”があります。
建物も、仏像も、器も、漆とともに受け継がれてきました。
こうした建築文化と修復の精神があったからこそ、
漆の技は途切れることなく、
1000年以上続く“日本の伝統技術”として残り続けているのです。
なぜ漆は日本の伝統技術と呼ばれるのか?
ここまで見てきただけでも、
漆が日本で特別に発展した理由が、だんだん見えてきます。
漆が「日本の伝統技術」と呼ばれる背景には、
素材・気候・文化の3つが、自然と重なり合っていたからです。
まず、日本の気候が漆に合っていたこと。
漆は湿度で固まる珍しい素材で、高温多湿の日本はその性質と相性がぴったりでした。
四季があり、湿気が多い環境だからこそ、漆の技術は無理なく根づいていったのです。
次に、日本は“木の文化”を持つ国だったこと。
家も器も道具も木でつくられていたため、
木を丈夫にし、美しく保つ漆は生活に欠かせない存在になりました。
木と漆は、ちょうどよい組み合わせだったわけです。
そして、日本人が大切にしてきた“直して使う文化”。
神社仏閣の調度品や仏像は、漆を使って修復し、
長い年月をかけて世代を超えて受け継がれてきました。
この「壊れても直して使い続ける」という考え方が、
漆の技術を途切れさせることなく磨き続けてきたとも言えます。
気候、暮らし、文化──
そのすべてが重なったときに、生まれたのが“日本の漆”です。
だからこそ、漆は「伝統技術」と呼ばれ、
今もなお、日本の暮らしの中に息づいています。
木軸ペンは“漆の技術を日常に持ち歩く”特別な道具

漆は、器や仏具といった身近な小物から、
寺院や城のような大きな建物まで、幅広いものに使われてきました。
それだけ、暮らしや文化に深く根づいた技術だったのです。
だからこそ、漆は“特別な場”だけに使われた技術ではなく、
日常の中から祈りの場まで、幅広く寄り添ってきたと言えます。
その長い歴史の流れの中で磨かれてきた漆の技を、
今では木軸ペンという小さな道具を通して、
気軽に、そして身近に味わうことができるようになりました。
毎日の筆記の中で、
1000年以上続いてきた漆の技がそっと寄り添う。
そんな贅沢を味わえるのは、
木軸ペンならではの魅力です。
木地師としての経験から感じる“木 × 漆”の相性

僕は木地師の家系で育ち、
仕事としても長いあいだ木と漆と向き合ってきました。
木と漆の職人として感じるのは、
漆は “木とともに育つ仕上げ” だということです。
木は一本ずつ違う表情を持ち、
同じ樹種でも、杢の出方や色合いがまったく異なります。
その個性に寄り添いながら艶を与えてくれるのが、漆の魅力です。
オイルの仕上げでは出せない深みや、
塗膜で覆う塗装とは違う“生きている質感”。
これは木の素顔を知っている木地師だからこそ、
より強く感じる部分かもしれません。
だからこそ、木軸ペンに漆を使うことには、
昔から木と漆を扱ってきた者としての確かな納得があります。
“木”と“漆”の組み合わせには、
千年以上続いてきた理由がある。
それを日常で感じられるのが、漆塗りの木軸ペンなんだと思っています。
まとめ
漆は、ただの塗料ではありません。
湿度に反応して硬くなり、木を守り、
時間とともに艶を深めていく、特別な素材です。
その漆が千年以上にわたって日本で受け継がれてきたのは、
日本の気候、木の文化、そして“直して使い続ける暮らし”があったから。
自然と人の営みが重なり合い、漆塗りという技が丁寧に育てられてきました。
そして現代では、
その伝統技術をもっとも身近に感じられる存在のひとつが、木軸ペンです。
伝統を大切にすることは、
必ずしも特別な場所で特別なものを扱うことではありません。
形を変え、日常の中で使っていく事も、
伝統工芸の伝えてく事において大切な事なのかなと思っています。
木軸ペンをきっかけに、
日本の伝統技術にふれる楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。
わたなべ木工芸では、国産の木を中心に一本ずつ丁寧に仕上げた木軸ペンをご用意しています。
気になる方は、ぜひこちらからご覧ください。